 あやまって放射線を浴びたらどうしたらいいのでしょうか? あやまって放射線を浴びたらどうしたらいいのでしょうか?
 被ばくの状況を記録し、また専門の医療施設を受診しなければなりません。 被ばくの状況を記録し、また専門の医療施設を受診しなければなりません。
一般の人が、あやまって放射線に被ばくするという状況は、ほとんどないと思われます。
しかし、仮に、何らかの事故で放射線被ばくを受けてしまったと想定してみます。
放射線源の種類、線源からの距離、被ばくした時間、被ばくした時に線源との間に何か遮蔽(しゃへい)なるものがなかったかどうか、そして被ばく後の症状などです。次に、病院で診察をうけなければなりません。
放射線の急性障害がまず一番問題になるわけですが、被ばくによる身体障害について関心を持っている医療施設は、一般病院では非常に少ないのが現状です。
全国的にみた場合、原発設置県では、原発事故に対処するために特定の病院が定められています。
放射線医学総合研究所
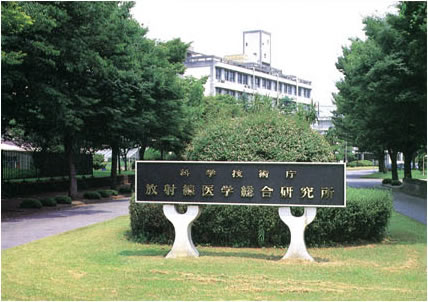 |
| 写真提供:放射線医学総合研究所 |
したがって、救急隊に確認して、指定されている救急病院に搬送して頂くことができます。原発設置県以外、あるいは指定病院が近くにない場合でも、最寄りの2次救急病院受診後、その病院から千葉県稲毛にある放射線医学総合研究所(放医研)に問い合わせ対処法を相談することができます。
病状の重篤度によっては、ヘリコプター(ドクターヘリ)を使い、患者を搬送することも可能です。
客観的に被ばく量を知るための検査としては、一般的にリンパ球数や染色体異常があげられます。
しかしある程度以上の被ばく量(リンパ球減少は500ミリシーベルト(mSv)以上、染色体異常も定量的には100ミリシーベルト(mSv)でないと変化はでません。
もし、被ばくをしてしまった可能性があれば、除染および場合によっては汚染拡大を防止するために医療のみならず、線量測定領域の専門家も含めた対応が必要になります。
監修:
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設 教授 奥村 寛
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 林 邦昭
執筆:
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設 助教授 難波 裕幸
|

